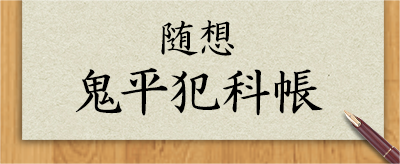第47回「瓶割り小僧」
今回は池波の自選作の第5話「瓶割り小僧」(文春文庫21巻)を取り上げ、その概要と感想を述べる。
この夏。1人働きの本格派の盗賊・高萩の捨五郎は、侍に斬られそうになった子供を助けたが、右膝を斬られる等危ういところを平蔵に救われ、密偵となった。そして密偵・彦十が住む本所二ツ目の軍鶏鍋屋・五鉄の部屋に同居し、足の回復に努めている。5日前の昼過ぎ、彦十に誘われ、長官が作ってくれた枇杷の杖をついて近所を一廻りし、弥勒寺前の茶店・笹やの縁台で、笠をかぶったままお茶を飲んでいた時である。彦十どん、絵師風の男がくるが、石川の五兵衛という大嫌いな盗め人だ、後をつけたらいいと早口で教え、捨五郎は茶店の中へ姿を隠した。彦十はすぐに後をつけ、男が山谷堀の船宿・伊勢新に入ったのをつきとめた。また捨五郎が五兵衛は1人働きの者を集め、畜生働きをしている様で、一度会ったが、話に乗らなかったといったので、平蔵は昨日の朝五兵衛を逮捕し、清水門の役宅の牢屋に収監した。
一夜明けて午前9時。五兵衛が詮議場の白洲へ引き出された。白洲の横手には小部屋があり、のぞき窓から秘かに詮議を見ることができる。平蔵は少し前に佐嶋筆頭与力を従え、小部屋へ入った。白洲では小林金弥与力が平蔵の命令で初めて詮議することになり、本名と生国を何度も尋ねるが、五兵衛は答えない。次第に小林与力の満面に怒りの血が登ってくる。他方五兵衛は両眼を閉じ、縄をかけられた胸を張っている。形の良い口元に薄笑いが漂う。年齢は27、8か。中肉中背、均整のとれた体に細縞の上田紬を着ている。そして左の耳から頬にかけて火傷の痕が色白の顔にくっきりと浮き上がり、美男だけに一種の凄味がある。その火傷の痕を、平蔵はずっと前にどこかで見た様な気がしたが、思い出せない。佐嶋、こうなれば仕方がない、明日は攻め方を変えてみよといって、一足先に小部屋を出た。外の石畳の通路を歩いていた小者の庄七が、急に現われた長官に驚き、盆の上の湯呑を落してしまった。その割れる音を聞いた瞬間、思い出したぞ、石川の五兵衛、と平蔵は片頬にかすかな笑みを浮かべた。
20年前の安永2年(1773)。平蔵は28歳であったが、京都町奉行の父・宣雄が病没したので、江戸へ帰り、家禄4百石を継ぎ、小普請組入りとなった。晩秋のある日、平蔵は麻布に住む旗本・曽我大膳を訪ね、帰路坂を下って神谷町に出た。そして知り合いの刀の研師・竹口惣助方へ立寄り、話をしていると、道をへだてた向う側の、小さな瀬戸物屋の前で事件が起きた。店先に並べられた4つの水瓶の傍で、4、5人の男の子が棒を振り廻し、遊んでいるので、破損を恐れた主人・梅吉が他所へ行って遊べと叱り、他の子はそうしたが、遊びを止めない子が1人いる。それが7、8歳の石川の五兵衛で、色白で端正な顔の火傷の痕が生々しかった。梅吉が大声で五兵衛を叱ると、おじさん、お客にひどい口をきくねとたしなめる。客だって、何を買うんだと梅吉が怒って聞くと、水瓶を2つ買って持って帰る、いくらだいと五兵衛が落ちつき払って答えた。6文にまけるが、その代りその手で2つとも持って帰るのだぞと梅吉が勝ち誇った様にいうと、いいともといい、4文銭を2枚出して、釣銭はいらないと敗けてはいない。この時店の中から梅吉の妹の夫で、赤松という若い浪人者が現われ、梅吉と並んで立ち、さも憎さげに五兵衛をにらみつけた。
しかし五兵衛は平気で、それじゃ持っていくよといって、道端の大きな石を抱き上げ、水瓶にぶつける。水瓶が音を立てて割れ、梅吉や見物人が思わず声を上げ、平蔵も土間に立った位だ。買った水瓶をどうしようと俺の勝手だ、割って破片にすれば、俺も1人で運べるよという五兵衛に、梅吉も赤松も反論ができない。また音がして2つ目の水瓶が割れた。そして何回かに分けて運ぶから、ここに破片を置いといておくれといい、2つ3つ破片を持つと坂道を麻布の方へ歩み始めた。
この時赤松が梅吉の傍を離れ、神谷町の通りの方へ向ったが、平蔵はその動きに殺気を感じる。すぐ子供を救うべく、赤松の後ではなく、五兵衛の後を追う。夕暮の旗本屋敷の間の細い坂道の彼方に、五兵衛の小さな姿が見える。五兵衛は本名音松という。母親は麻布坂下町で茶店を出しているが、父親は4年前に病死した。昨年の夏、継父ができたが、すぐ暴力を振う男で、五兵衛の火傷も継父に薬罐を投げつけられてできた。だが母親は別れられず、五兵衛には小遣いを持たせ、いつも外で遊ばせる。坂を登り切ると、六本木から竜土町へ通じる道へ出るが、五兵衛はその道を渡り、鼠坂を走り下る。その時先廻りした赤松が坂の途中から出て、五兵衛を突き倒し、大刀を振りかぶって斬ろうとする。間一髪、平蔵の投げた小石が赤松の顔へ命中し、たじろぐ赤松に平蔵が走り寄り、子供を斬って何になると叫び、刃風をかわし、胸下に拳を突き入れた。一方五兵衛にも立てと命じ、大人を馬鹿にするな、わかったかと叱り、いきなり五兵衛を抜き打ちにする。声もなく倒れた五兵衛をそのままにして、平蔵は気絶した赤松をかつぎ、坂を下っていった。しばらくして五兵衛が蘇生し、立ち上ると、着物と帯が2つに割れて落ち、まげを失った前髪が顔にたれる。裸の少年が髪を乱し、悲鳴を上げながら坂を走り下っていった。
翌朝の9時。再び五兵衛は詮議場の白洲へ引き出された。ただし長官自らが詮議をするということで、佐嶋、小林以下4名の与力、同心5名が列席しているが、五兵衛は薄笑いを浮べつつ莚に座っている。やがて平蔵が20年前と同じ黒紋付の羽織・袴という姿で現われた。下げた顔を上げた五兵衛は平蔵をどこかで見たと感じたが、平蔵はじっと五兵衛を見たまま声をかけない。五兵衛も見返す内に、その薄笑いがたちまち消えた。その瞬間、平蔵は瓶割り小僧、到頭、盗っ人に成り下ったかとじわりという。驚愕の余り声も出ない五兵衛に、想い出したか、鼠坂のことを、恐ろしさの余り、泣き叫んで逃げた気持ちを忘れたのかと問い詰める。がっくりと肩を落し、うなだれた五兵衛はもはや昨日の五兵衛ではなかった。門番小屋へ来ていつも食べさせてもらっている黒い野良猫が、塀の上から白洲の有様を見物している。五兵衛がすべてを白状したのは、中休みを取り、夕方近くであった。
その日の夕餉に平蔵は佐嶋、小林の2与力を相伴させた。小林が誠にもって面目次第もございませんと両手をついて謝まると、まあ呑め、のう小林、五兵衛は一筋縄ではゆかぬ、ただわしは五兵衛の弱味を握っていたので、うまくいったのだ、まあ聞くがよいといって、干した盃を置き、亡父遺愛の銀煙管に煙草をつめながら、20年前の事件を2人に話した。そして五兵衛は16の頃継父を殺し、母親を捨てて他国へ逃げたと申していたのう、もう少し、誰かが目をかけてやればよかったものを、と話を結ぶのであった。
以上が概要であるが、以下感想を述べれば、池波は昭和54年4月、毎日新聞に「少年のころ」という随筆を載せ、次の様に述べている。私は大正12年1月に浅草聖天町で生まれた。すぐに関東大震災が起き、父母と共に浦和に移り、数年過したが、これが最も平穏な明け暮れが続いた数年間であった。やがて東京へ戻った父母は、7歳の時に父の店の倒産もあって、離婚した。更に母は再婚に失敗し、弟を生んで永住町の実家に戻り、2人の子のため働き出した。私も小学校を出てすぐに働いたが、振り返ると、浦和では父母も落ち着いて暮し、私は野や森を駆けまわり、好きなだけ絵本やクレヨンを買ってもらい、清潔で質素に育てられた。私の一生も性格もこの数年間で定まった。自分の心身の底に生き続ける子供のころを、私は今後の自分の小説へ表現していきたい。そして翌55年9月に発表されたこの小説は、この子供のころの大切さを見事に表現していると思われる。
次に池波は同じ54年の8月、毎日新聞に今度は「猫」という随筆を載せ、次の様なことを書いている。先頃、月刊誌の連作小説を15枚程書いたところで、ハタと行き詰った。いつも1日か2日で壁を突き破れたが、5日も6日も先へ進まぬ。そうしたある日の夕暮、応接間から見ていると、飼い猫・ネネが道路に面した塀の上に腹ばいとなっており、空間の一点を見つめたまま、身じろぎもしない。おい、ネネ、何を考えていると呼びかけると、ネネは物憂げにこちらを見て、再び顔をそむけた。その瞬間私はその場面に猫を登場させると、壁に穴が開いて小説が結末に向うと感じた云々。それがこの小説の、黒い野良猫が塀の上から白洲を見物している場面で、見事な効果をあげている(以上参考池波正太郎「私が生まれた日」朝日文芸文庫)。
最後にこの小説も江戸切絵図に則り町や坂の名が書かれている。現在神谷町、麻布坂下町、竜土町がなくなったのは残念であるが、鼠坂が残っているのは嬉しい限りである。なにしろ「瓶割り小僧」だけでなく、「麻布ねずみ坂」(文春文庫3巻)、「麻布1本松」(同21巻)等で平蔵が活躍した坂であるから。(続く)


 メニュー
メニュー 閉じる
閉じる