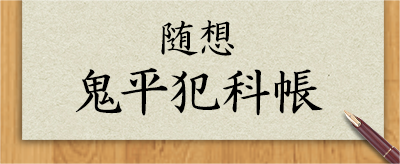第23回『番外編 乳房(上)』
天明元年8月17日、浅草田原町の足袋問屋加賀屋の女中で19歳のお松は、加賀屋の娘お千代のお供をして池ノ端の小間物屋丁字屋へ入った。お千代が買物に熱中している間、ふと外をみると店の前を勘蔵が通り過ぎた。
勘蔵はお松が17の時に好きで一緒になった深川の腕の良い煙管職人であった。一生懸命尽したが、彼は1年前「お前は不作の生大根のような女だ」とののしり、姿を消した。捨てられたお松に同情した人達が加賀屋で働けるようにしてくれたのである。
お松はすぐ外へ出て憎悪に未練が入り混じった想いで後をつけると、勘蔵は入谷の百姓家へ入った。戸が開け放しになっているし、周りに人もいない。お松は中を見たくなり、恐る恐る入っていくと、勘蔵が部屋で
台所に、鍋釜がある。部屋にたんすもある。鏡掛けもある。そして壁には女の着物が掛っていた。それを見た瞬間、全身の血が頭に昇り、お松はたんすの中から絞りのしごきをつかみ出し、男の首に巻きつけ、胸の上に
お松がわれに帰った時、勘蔵は息絶えていた。腰がぬけ、勘蔵の傍にへたり込んだまま、動けなかった。長い時間が経ち、
翌日の午後、下谷茅町で小間物屋をしている長次郎が下北沢の叔父の病気見舞の帰路、駒場野へ来ると、気を失った女(お松)が倒れていた。ひどい熱がある。長次郎は道玄坂の知り合いの茶店へ女を担ぎ込み、老夫婦に一両を出して世話を頼み、明後日くるからといって帰っていった。お陰でお松は夜になって正気に戻った。
同じ日、西の丸書院番をやめて待命中の長谷川平蔵が小川町の妻の実父の病気見舞の帰途、急に駒形の御用聞の三次郎に会いたくなった。若かりし日、平蔵は継母から憎まれ、本所の家を飛び出し、無頼の群に身を投じていた時期がある。その時三次郎は町民を苦しめる無頼の徒を懲らしめる平蔵をお縄にしても、いつも意見をして釈放してくれていたのである。
久し振りに再会した平蔵は、昔の口調で、親分、今日は何か悪い事件が起きたのかと尋ねると、三次郎は加賀屋のお松の事件をあげた。詳しく聞くと、お松は深川の漁師の娘で、左頬に酔った父親が庖丁で切りつけた傷跡がある、17の時父親が死に、魚貝を売って1人で暮していたが、深川の煙管師勘蔵という悪い男にひっかかった、そいつがまたお松をそそのかし、一緒に逃げたのだと思う、とのことであった。
屋敷に帰った平蔵はすぐ亡父が収集した煙管を調べたところ、やはり深川の勘蔵作の煙管があった。ただ年代からみて、今の勘蔵はこの勘蔵の息子であると思われたので、平蔵はすぐ手紙を書き、三次郎に知らせおいた。
それから半月後三次郎が平蔵の屋敷を訪ねてきて、お松をひっかけたのは、やはり先代の勘蔵の倅であったが、その頃勘蔵は労咳(結核)が進み、やけになって大酒を飲み、仕事もしなくなってしまった。しかしお松はそんな男の世話を本当によくしていたと報告をしてくれた。これを聞いた平蔵は、「なあ親分、お松のような女は昔から絶えたことがない。今の世では、損をするのが女ばかりだ」と三次郎にしみじみというのであった。(以下次号に続く)
(『乳房』昭和59年文芸春秋刊)


 メニュー
メニュー 閉じる
閉じる