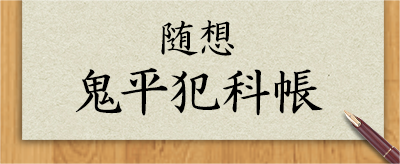第60回「秘密と越中・井波(4)」
長編時代小説「秘密」(文春文庫)の、越中・井波関係の、4番目の原文と備考の続きをお読みいただきたい。
[原文の4](前略)
「道を歩いて行くと、軒をつらねた木彫り師の家から、
[備考の4]最初に原文の「人の情がこまやかで、井波は、そのような、よいところ」という宗春の説明は、池波が昭和56年に初めて井波を訪れて書いた「随筆」の中にある、二つの文章をもとに書かれたものである。
一つは、浅草の
もう一つは、それから二日後の朝、旅荘の2階から通学中の小学生の男の子を見ていると、「その子は帽子をとって挨拶をするではないか。見も知らぬ旅人の私にである。一昨日の老婦人の言葉が、いまさらながらおもい起された」(「私が生まれた日」朝日文庫160頁)という文章である。
次に池波はこの様な人情のこまやかな先祖の地・井波が大好きになり、その後何度も井波を訪ね、人々と親しむ。その一人で最も親しかった
[原文の5](前略)
片桐宗春は、井波へ立ち寄ると、町医者・
「何、
[備考の5]勝庵は久志本長順の「われらが必ず、おぬしを守り通してみせる」という言葉に打たれ、宗春の井波行に賛同する。しかし明朝までの間に襲われる恐れもあり、三人は用心をして語りあかすことになる。
最後に、少々長いが、5番目の原文と備考をお読みいただきたい。
[原文](前略)
「若先生。三年ほどのうちに、私の方から白石を連れて、一度、井波へまいりますよ」(中略)
「それは、うれしい。その日を、いまからたのしみにしています」
のむうち、語るうちに、夜明けが近づいてきた。(中略)
宗春が奥の部屋へ行くと、おたみは、ぐっすりと眠っている。
「おい、これ……おたみ」(中略)
「は、はい」
「よく眠れたか?」
「あい。夢も見ませんでした」
「何よりだ。さ、起きて仕度を……」
「ほんとうに、先生と旅に出られるのですねえ」
「そうだ」
「まるで、夢のような……」
おたみの顔に、生き生きと血の色がのぼってきた。(中略)
片桐宗春とおたみは、勝庵宅を出た。(中略)二人より先に、白石又市が出て、あたりの様子をうかがいつつ、
二人と共に、見送りの勝庵が歩む。(中略)三人が千住大橋の南詰めへ出ると、白石又市が待っていた。(中略)
「勝庵どのと共に、井波へおいで下さい。ぜひとも……」
「はい。必ず」
早朝のこととて、長さ六十六
「さらばでござる」
「若先生。おしあわせに」
白石は、無言で頭を下げた。
宗春とおたみは、大橋を北詰めに向って歩む。その途中で、二人は振り返り、勝庵と白石へ一礼した。(後略)(「秘密」文春文庫339頁-341頁)
[備考]荒川から大川にかけての


 メニュー
メニュー 閉じる
閉じる