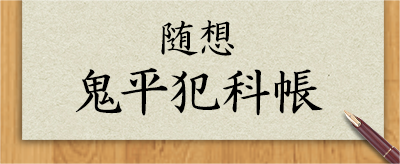第15回『平蔵の女性観』
鬼平犯科帳には、平蔵の妻・久栄、異母妹のお園、密偵のおまさ、荒神のお夏等の43人の盗賊等大勢の女性が登場し、活躍する。次回からこれら女性達と平蔵の物語を書くこととするが、今回は平蔵の女性観、すなわち池波の女性観を以下著書から引用して述べておきたい。
第1に、女性は現在しか考えない。それが女性のいいところであるが、つい「我欲」となって表われる。
しかし平蔵の時代は違う。侍も町人も自分の女房に敬意を持っていたし、女房も夫に敬意を持っていた。
平蔵の場合、「見回りに出てくる」といって出たら何が起こるか分からない。何か起こって責任を取ることは切腹することである。常に死を覚悟して生きている。だから毎日を「これが
これからの時代は、自分だけよければいい、人のことはどうでもいいという「我欲」ばかりでは、やっていけなくなる。小は家庭から大は企業まで、共存共栄の集まりだという感覚を持たなければ生き残れないと思う(『新私の歳月』講談社文庫。昭和61年)。
第2に、似たもの夫婦では成長も充実もない。夫唱婦随とは、その夫が主体となりうる本質を持っている家庭のみ通用する。夫が無能で妻が有能であっても、夫の横暴に従えということは、家庭の完成にはならぬ。むしろ破壊である。妻の有能を認めぬ夫は、さらに無能である(「富氏遺筆」昭和30年前後に書かれたメモ。『完本池波正太郎大成』別巻)。
第3に、昭和20年7月、海軍美保航空基地にいた池波は母から手紙を貰い、次のような短歌(訳は筆者)を詠んでいる。
○江戸ものの心忘れず国のため 強く生きむと母はいうなり
(江戸ものは空襲があっても逃げず、国のため府立第一高女の仕事を続け、強く生きると母はいう)
○
(離婚して6歳の自分と実家に戻った母、子供のために殺気立って働いた母、小卒でも活躍できると株屋に就職させた母。そんな強い母を今改めて想い出す)
○爆撃に
(母は女学校の購買部で働きながら祖母、叔母、弟を養っていたが、空襲が激しくなり、浅草の実家も移転先の田端、京橋の家も焼けてしまった。しかし奇蹟的に焼け残った下谷稲荷町の家を見付け、今も3人を養いながら東京で働いているとは)
○爆弾の下に横たう
(美保航空基地にも空襲が日に3、4度あり、死亡者が増えはじめ、日本は今爆弾の下にあるが、力の限りをつくして母と一緒に生きてゆきたい)
(「三昧」昭和19年、20年の俳句、短歌、随筆集。『完本池波正太郎大成』別巻。『青春忘れもの』中公文庫)。
第4に、池波は5、6歳の頃母に連れられ、初めて洋画を見た。以来洋画で女性に対する礼儀や男同志の友情等大切なものを学んできた。これがなければ、今の自分はなかったという。また平成元年に「ワーキング・ガール」というシガニー・ウィーバ主演の映画を見たが、会社が差別世界であることも分かり、約2時間が少しも退屈ではなかったと述べている(「映画は私の大学」。『完本池波正太郎大成』別巻。『池波正太郎の銀座日記』新潮文庫)。
第5に『青春忘れもの』(中公文庫)によれば、池波の父の姉は吉原の老妓で、日本画家・尾竹国観(明治13年―昭和20年)の二号さん(原文のまま)であった。その国観の兄・
ところでこの竹坡は明治44年9月に平塚らいてう等により創刊された、日本初の女性文芸誌『
竹坡は吉原には解放すべき女性が沢山いると考えていたので、らいてうや姪を案内して一人の女性の話を聞かせたところ、各紙が「青鞜社の女豪連が吉原で豪遊」などと興味本位の報道を繰り返し行ったので、社は世間から激しい非難攻撃を受ける事態となった。
大正5年2月、『青鞜』は通巻52号で廃刊したが、日本の女性解放運動の出発点となった。池波も竹坡がこれを支援したこと、国観、竹坡の姪が青鞜の志を捨てずに生涯女性文芸活動を続けたことを、後年知ったに違いないと思う(『あざみの花』高井陽・折井美耶子。ドメス出版)。


 メニュー
メニュー 閉じる
閉じる