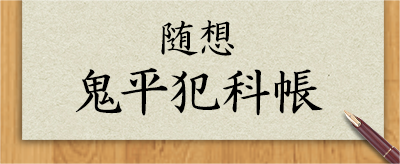第16回『瓶割り小僧』
『瓶割り小僧』(文春文庫21巻)は、子どもの頃が人間にとっていかに大事であるかを示唆する、自選作の1つである。
石川五兵衛という盗賊が捕らえられたが、一言も口をきかぬというので、取調べの様子を横の小部屋から鬼平が盗み見ると、左横顔に火傷がある。どこかで見たことのある男である。外へ出ると、小者が鬼平に驚いて湯呑みを落とし、それが割れた瞬間に想い出した。
約20年前、神谷町の
麻布では母親が茶店をやっていたが、4年前、夫の病死後一緒になった年下の男が利発な子どもを嫌い、薬缶を投げて火傷をさせるなどの暴力を振るっていた。
「大人の男は皆知恵が足りない。継父もそうだ。何で母は好きになったのだ」と思いながら子どもが歩いていくと、瀬戸物屋の用心棒が追いついて斬ろうとしたが、間一髪のところを鬼平が助けた。
しかし、鬼平は子どもを立たせ、「大人を馬鹿にするなよ」と言っていきなり抜き打ちをした。子どもはしばらくして息を吹き返し、立ち上がると、着物と帯が2つに割れて下に落ちたので、悲鳴を上げて、裸のまま走って逃げた。
翌朝、石川は直々取り調べに当たった鬼平を見ても薄笑いをしていたが、しばらくしてそれが消えたとき、「瓶割り小僧。盗っ人になったのか。あのとき泣いて逃げた気持ちを忘れたな」と言うと、石川はがっくり肩を落とし、それから犯行をすべて白状した。
その日の夕方、鬼平は部下に言った。「あやつは16のとき継父を殺害し、母を捨てて逃げた。いま少し、だれかがあやつめに目をかけてやればよかったものを」
なお池波は、この小説が昭和55年9月に発表される1年5ヵ月前に、次のような随筆を発表している(『私が生まれた日』朝日文庫)。
関東大震災で浅草の家が焼け、私は浦和で0歳から5歳まで過ごした。振り返ってみて、浦和でのおだやかな幼時の生活が今日の自分へ大きな影響をもたらしている。父も母も落ち着いて暮らし、健康であり、私は野や森を駆け回り、好きなだけ絵本やクレヨンを買ってもらい、清潔にしかも質素に育てられた。私の一生はこの数年で決定し、性格も浦和で定まった。6歳の時に父母が離婚した後、何度か横道にそれかかったが、そうはならなかった。今も自分の中に生きている「子どもの頃」をこれから小説に表現していきたい。


 メニュー
メニュー 閉じる
閉じる